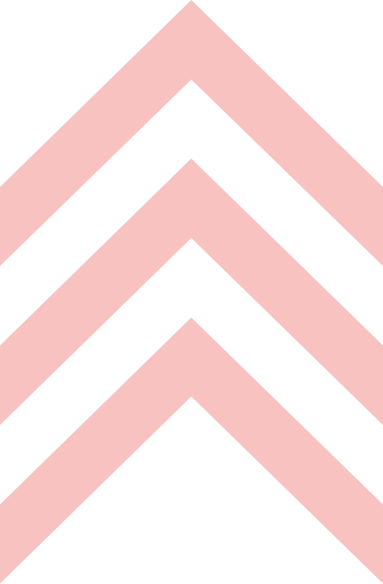
イジンデン コラム 第19廻
ロシアの大変革者 ピョートル大帝
今回のコラムで紹介する人物はピョートル・アレクセイヴィチ・ロマノフ(1672~1725)。あるいはピョートル大帝の方が通りがいいかもしれない。この大帝こそがロシアを東方の一国家から、ヨーロッパの一等国に飛躍させた人物である。今回はこの「大帝」の事績を追っていきたい。 ①「大帝」の不遇な少年時代? しかし、ピョートルの人生は初めから順風満帆であったわけではない。父帝アレクセイは前妻マリア・ミロスラフスカヤと後妻ナタリア・ナルィシュキナの両者との間で子を設けており、このどちらを後継者につけるかで争いが生じたのである。ナタリアの子であったピョートルは父帝が死去した時いまだ 4 歳であったが、ナルィシュキン派はさっそく彼を後継者に推した。マリアの息子であったフョードルとイヴァンがともに病弱だったため付け入る隙があったのだ。 両者の対立はツァーリの居城たるクレムリンに血を流すに至ったが、最終的にはイヴァンとピョートルが共にツァーリになることで妥協が図られた。しかし実権は摂政となったイヴァンの姉ソフィアとその寵臣の手中に収められ、ピョートルはモスクワ郊外のプレオブラジェンスキー村の館で母親と暮らすことになった。彼は政治の中枢からは遠ざけられ、帝王学を学ぶ機会も与えられなかったのである。 ただ一方で正規の教育を受けなかったことは、伝統や儀礼に囚われないメンタリティを醸成する一因になった。また村での生活の間に彼は後に腹心の部下となるメーンシコフを登用し、模式的な軍隊を作って死傷者が出るほどの厳しい訓練を行った。さらにモスクワ郊外にあった「外国人村」へ出かけ、西欧の事物を吸収していった。ピョートルの「改革者」としての素養は少年時代から培われていたといえよう。
②皇帝自らヨーロッパ視察へ!
ピョートルにとって風向きが変わり始めたのは、ピョートルが 15 歳の時であった。摂政ソフィアの進めた二度のクリミア遠征が失敗に終わると、その権力基盤は揺らぐこととなったのである。これに対しピョートル派は1689年、彼が17歳の時にピョートルをエウドキア・ロープヒナという貴族の娘と結婚させる。ピョートルを結婚ができる成人とすることで、その後見人である摂政職の大義名分を失わせることができるからだ。摂政ソフィアは危機感を覚え、ピョートル暗殺の陰謀を企てるも失敗する。彼女は修道院に幽閉され、ピョートルは歴史の表舞台に戻ってきた。しかし彼が実際に親政を開始するのは母親のなくなった1694年からである。
親政を開始したピョートルが最初に行った大事業は、南方つまりオスマン帝国との闘いである。当時のオスマン帝国は黒海やアゾフ海をも勢力圏下に入れており、ロシアは南方への進出を阻まれていた。前述した遠征もこれを打破するために行われたものである。ピョートルは自らも砲兵下士官として戦場に立ち、1965年に遠征軍はアゾフの要塞を包囲したが、海からの補給に頼る要塞を落すことができずにいたところを後方から襲われ、第一回の遠征は失敗に終わった。しかしピョートルはそれであきらめることはなく、弱点であった海軍を急ごしらえで整え、翌年には再度要塞を包囲しこれを陥落させたのである。強大なオスマン帝国に対する勝利は若きツァーリの威信を大きく高め、古代ローマ風の凱旋門さえ建てられたのだった。
この戦勝の翌年の 1697 年、西欧への大規模な使節団が組織される。その数、総勢 250名。しかもツァーリ自身もお忍びで参加するというのであるから、前代未聞である。使節団の第一の目的は対オスマン帝国の協力関係を西欧諸国と結ぶことだった。アゾフでの戦闘に勝利したとはいえ、いまだオスマン帝国はロシア単独では太刀打ちできない強大な相手であった。しかし、オスマン帝国との最前線に立っていたオーストリア帝国は、1683 年から続いていた大トルコ戦争がようやく終結に向かい、和睦の協議をしていたところであったから、ロシアと対オスマン同盟を結ぶことはなかった。その他の諸国とも対オスマン同盟という点では何らの成果もあげることはできなかった。
だが使節団の目的はもう一つあった。それは西欧の進んだ技術や文化を吸収することである。そしてピョートルは自ら実践しそれらを吸収したのである。オランダではピョートル自らが船大工として働き、ライデン大学の解剖学講義に強い関心を寄せた。またオランダの整然とした街並みは後の新都市建設に活かされることになった。次に、ロンドンに渡りウィンザー城や上院議会などを見学した。当時最高の科学者であったニュートンやハレーとも会見を行っている。特にピョートルの目を惹いたのは、ポーツマスでの海軍演習である。ここで彼は「ロシアの皇帝であるよりは、イギリス海軍の大将でありたい」と惜しみない賞賛を送った。使節団としても武器、工作機械、時計などの西欧の先進的事物を購入し、数十人のお雇い外国人も登用した。
しかし、視察中のピョートルの耳に驚きの知らせが飛び込んでくる。首都モスクワで銃兵隊が蜂起したというのである。この知らせを聞くとピョートルは本国の安定を取り戻すため、視察を切り上げて帰国の途についた。ピョートルが帰国したときには、すでに銃兵隊の反乱は鎮圧され、3000 人が逮捕、100人が処刑された。ピョートルはこれに満足せずさらに苛烈な対応を行い、追加で 1182 人を処刑、601 人をむち打ち後に追放した。これはピョートルの自らに逆らうものは決して許さないという態度の表れである。
また帰国直後にピョートルは自らを出迎えた貴族の顎ひげを切り落としたという話がある。長い顎ひげはロシアの伝統であり、ピョートルはそれを改めるという意思を行動で示したというわけである。事実彼は「ひげ税」を導入し、また洋服の着用や暦をイギリスで用いられていたユリウス暦に変更した。
こうしてロシアはピョートルの非常に強力なリーダーシップの下で西欧化改革が行われていくことになったのである。
③戦争と改革の時代―ロシア「帝国」の成立
さてピョートルのロシア強国化政策の次なる目標はスウェーデンの撃破であった。先述したように南のオスマン帝国包囲網を作ることができなかったために、ピョートルはその目を北に向けたのである。当時のスウェーデンは北ドイツ沿岸や現在のバルト諸国をも領土とする「バルト海帝国」として北方で覇を唱える軍事強国であったが、それゆえに周辺諸国から危険視されていた。すでにピョートルは使節団の帰国途上でポーランド国王と密談していた。またデンマークにも使者を送っている。ロシアも含めた三国はいずれもスウェーデンに敗北して領土を失った国々であり、この三国が協力してスウェーデン包囲網を結成したのである。
1700 年 8 月、オスマン帝国とも和睦し後顧の憂いを断ったロシアはスウェーデンに宣戦布告を行った。しかし緒戦は惨憺たる有様。9 月にはロシアはスウェーデンのバルト海における重要拠点ナルヴァ要塞を包囲したが、そこから 2 か月半手をこまねいているだけであった。一方のスウェーデンは、少数の精鋭部隊を用いてデンマーク首都コペンハーゲンを占領。デンマークを戦線から離脱させ、その足のまま海路ナルヴァに向かった。スウェーデン軍を率いていたのは国王カール 12 世、古代のアレクサンドロス大王を崇拝する天才的指揮官であった。ナルヴァでは、およそ3万4千、三倍の数を擁するロシア軍を徹底的に打ちのめし、ロシアは 5700 人が戦死、149 門の大砲すべてを失う惨敗を喫した。ピョートル自身はこの時軍勢を離れていたため難を逃れていたが、このままスウェーデン軍が侵攻してきたら一たまりもない。
だが運はピョートルに味方した。カール 12 世はロシアの前にポーランドを倒す戦略を採ったが、これがなかなか手間取り結局ポーランド戦に勝利したのは約 3 年後の 1704 年2 月であった。この貴重な 3 年の間にロシアは態勢を立て直すことができたのである。カールはなぜロシアにとどめを刺さなかったのか。その理由はわからないが、いずれにせよこの戦争はロシアの勝利に終わることになる。1707 年秋にようやくカール 12 世はロシアに軍を進め、一路首都モスクワを目指す。ロシアの「焦土作戦」、ロシア支配下のウクライナとスウェーデンの同盟など様々な展開がありつつも、両軍はウクライナのポルタヴァ要塞を決戦の地とした。1709年6月27日に行われたこの決戦は、しかし一日にして勝敗が決した。ロシア軍損害1650人、スウェーデン軍損害約7000人。ナルヴァの借りを返す、ロシア軍の大勝利であった。カール 12 世は命からがら、オスマン帝国のベンデリという町に逃れた。
しかし戦争はまだ終わったわけではない。オスマン帝国に亡命したカールはその後もオスマンのスルタンに対してロシア攻撃を嗾けた。だが 1714 年には新設されたロシア・バルト海軍がハンゴー沖でスウェーデン海軍を撃破し、海でも優位を握っていた。その後も同盟国間の領土問題や、列強の介入によりすぐには和睦は結ばれなかったが、1721年にはニスタット条約が結ばれ、ロシアは現在のバルト三国、カレリアの一部を獲得し、スウェーデンに代わって地域一の強国としての立場を手に入れることができたのである。
この勝利を祝って、ピョートルは元老院からラテン語の「皇帝(インペラートル)」の称号を与えられ、ロシアは「皇帝」が治める「帝国」となった。また同時にピョートルは「大帝」という称号も与えられた。こうして「ピョートル大帝」と「ロシア帝国」は共に誕生したのである。
一方でこの時期のピョートルは戦争のみを行っていたわけではない。同時にロシアという国の仕組みを抜本的に変える改革を推進していた。その根幹にあったのが新首都サンクトペテルブルクの建設である。建設が始められたのは早くも戦争初期の 1703 年 5 月。モスクワ北方のネヴァ川河口。だがこの地は地盤が良くなく、洪水の恐れもあった。このような不便な地を新首都建設の地に定めたのは、何よりもモスクワの古臭い伝統にとらわれることなく改革を行うために他ならなかった。
特筆すべきは役所の再編成である。従来モスクワの行政は「官署(プリカーズ)」と呼ばれる諸官庁が担っていたが、業務の重複や規模の差異がありうまく機能しているとは言いがたかった。そこで遷都に合わせて、諸官庁を当時ヨーロッパで流行していた「参議会(コレギウム)」へと改編したのである。この役所においては、ロシア人以外にもお雇い外国人が多く働いており、全体のおよそ10%がお雇い外国人であったと言われる。参議会は各参議会に設定された規則と「総則」に従って動くとされた。実際には皇帝直属の「官房」が職権を超えた権力を持っており、すべてが規則通りであったわけではないが、それでもロシアは先進的行政組織によって運営されることになったのである。またこれまで皇帝とは一定の距離を保って自立してきた教会組織も国家の一行政機関として組み込まれることになった。この「宗務院」と呼ばれる組織の長は聖職者ではなく、皇帝によって任じられる俗人であったため、教会は皇帝の監視下に置かれたと言える。
戦争と改革。ピョートルはこの二つを通じてロシアを急速にヨーロッパの一等国に成り上がらせた。
④大帝の残したロシア
確かにピョートルはロシアを急成長させた。だが反面では、このような急速な変化が人々の反感を買うのも必然である。
そしてそれは彼の実の息子、皇太子アレクセイもそうだったのである。彼はピョートルの一人目の妻であるエウドキアの息子であったが、エウドキアがほとんど無理やりに修道院に入れられ、事実上の離婚をされたことは、父と子の間の確執を生むのには十分であったと思われる。またアレクセイは気質としてピョートルの改革に不満を持ち、むしろ正教などのロシアの伝統的な文化を好んでいた。反ピョートルの貴族や聖職者がアレクセイに期待をかけるのは自然な成り行きであった。
そんな最中、アレクセイが愛人と共に親戚であったオーストリア皇帝カール 6 世のところへ亡命するという事件が起こる。アレクセイは交渉の後に帰国するが、ピョートルはこの事件を外国勢力の力を借りた現政権転覆の陰謀と考え、アレクセイ自身を含む反ピョートル派の貴族や聖職者を多数処罰した。アレクセイにも死刑判決が下ったが、刑執行前に獄中で死亡した。「陰謀」が実際にあったのかについては多くの疑問が残るが、アレクセイ自身としてもピョートルの改革を廃止するという大まかなプランは持っていた。自らが死ねば、改革が無に帰すのではないかというピョートルの懸念は確かだっただろう。それゆえにピョートルは自らの望むものを男女の区別なく後継者に指名できるという布告を出す。18世紀のロシアにはエカチェリーナ1世、エリザヴェータ、エカチェリーナ2世と相次いで3人の女帝が君臨するが、それはピョートルの布告が原因であった。
また不満を持っていたのは貴族や聖職者だけではなく、民衆もであった。むしろ民衆たちこそがピョートルの改革における最大の被害者であった。スウェーデンとの戦争に勝つために1705 年には徴兵令が施行され、20 世帯につき一人を提供することを全国の村々に命じた。この世帯数は後に 40⇒75 と次第に緩和されるが、徴兵制自体はずっと継続された。また当時の徴兵制では徴兵の期限は無期限であった。こうして総勢約 25 万もの大軍団が組織されたが、ピョートルはこの軍団を戦後も維持することを望んだ。そのために新しい人頭税による税制度が施行され、そこからの収益はすべて軍隊の維持に充てられたのである。またサンクトペテルブルクは先述したようにあまり良い地形とは言えず、都市建設には多大な労力と犠牲が必要とされた。そしてそれを担ったのも各地から強制的に集められてきた民衆たちであった。6万とも10万とも言われる犠牲者を出したサンクトペテルブルクを、カラムジンは屍の上に築かれた都市と非難している。
結局のところピョートルの改革は何をもたらしたのだろうか。確かにロシアは強国となった。しかし民衆はその成果を享受するどころか、ロシアが強国となるための下敷きにされていたのである。また西欧文化の吸収はロシアが西欧列強に認められるためには必要だった。しかしその性急さは既存のエリートたちのアイデンティティを揺さぶり、19 世紀に巻き起こる西欧派とスラブ派の一世紀にも及ぶ思想対立の原因となった。これらの点は現代のロシアにおいても問題となっている事柄であり、ある意味で現代ロシアの諸問題の一つの原因はピョートルの改革にまで遡ると言えるかもしれない。だがその評価をどのようにつけるとしても、ピョートルは自らの強固な意志で国家を牽引して、国家を抜本的に変えることができた稀有な人物であり、その事例を知ることは決して無駄にならないはずである。
〇参考文献
土肥恒之「ピョートル大帝-西欧に憑かれたツァーリ」(山川出版社、2013)
栗生沢猛夫「図説ロシアの歴史」(河出書房新社、2010)
文・早稲田歴史文化研究会






